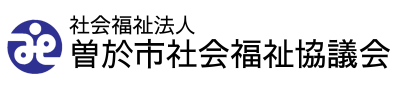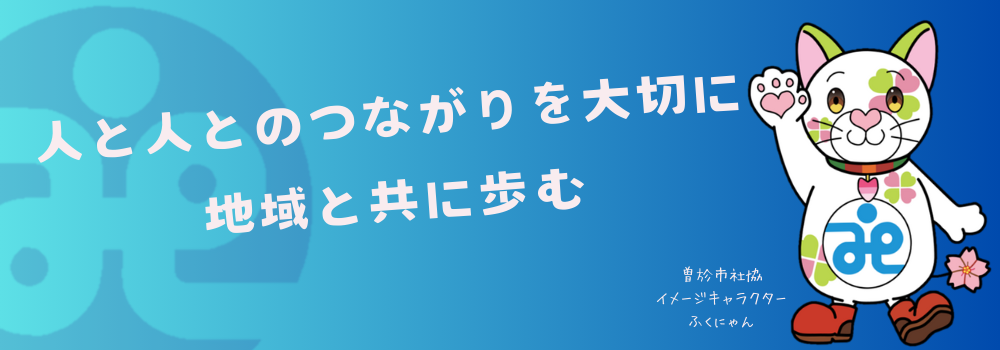社会福祉協議会(社協)とは
誰もが安心して暮らし続けられる「福祉のまちづくり」を目指して、各種の福祉サービスや相談援助活動、ボランティア育成やボランティア・市民活動の支援、地域福祉活動の支援など様々な場面をとおし、住民の皆さんと一緒に地域福祉の推進に取り組んでいます。
また、それぞれの地域では、住民により校区社会福祉協議会が組織されており、地域の実情に応じた住民主体の地域福祉活動が取り組まれています。
~公共性の高い民間団体~
社会福祉協議会の介護保険制度での位置づけは、事業を実施する一民間企業者ですが、
一方で住民ニーズ・福祉課題の明確化、住民活動の推進機能、公私社会福祉事業等の組織化・連絡調整機能といった公益性・中立性が求められています。
社会福祉協議会の基本的性格
社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に、「その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。」という要件があるように、地域で暮らす住民の皆様や福祉、保健・医療、教育等の関連分野の関係者、さらに地域社会を形成する様々な専門家・団体・機関によって構成されています。
地域が抱えている様々な福祉課題を地域全体の問題として捉え、みんなで話し合い、協力して解決を図ることを目的とし、人と人とをつなぐ地域のコーディネーターの役割を担っています。
そして、その活動を通して、個人が尊厳をもって地域や家庭の中でその人らしい生活を送れるように支える「福祉のまちづくり」を推進しています。
社協活動の5つの原則
- ● 住民ニーズ基本の原則
社協の活動・事業の原点は一人ひとりの住民のニーズであり、多様な方法で把握し、それに基づく活動を進める。 - ● 住民活動基盤の原則
社協は、住民の思いや、主体的な取り組みを基盤として活動・事業を進める。
活動・事業を実施する際は、常に住民同士、住民と地域の関係者のつながりや支え合い、参加の機会を育むことを支援する。
- ● 個別支援と地域づくりの一体的展開の原則
一人ひとりのニーズに基づく相談・生活支援等の個別支援と、住民や地域の関係者が主体的に参画する地域づくりを連動・循環させながら展開する。 - ● 民間性の原則
民間組織として開拓性・即応性・柔軟性を発揮し、既存の制度にとらわれず、柔軟にニーズに対応するとともに、必要に応じて既存サービスの改善や新たな社会資源の開発、民間財源の確保に計画的に取り組む。 - ● 連携・協働の原則
多様な地域生活課題を受け止め、対応するとともに、住民や地域の関係者による主体的な活動を推進するため、福祉関係のみならず、医療、保健、就労、住まい、司法、産業、教育、権利擁護、多文化共生、防犯、防災など多分野の関係者と連携・協働する。
住民の福祉の増進を図ることを基本とする行政とのパートナーシップを構築し、役割分担に基づき、協働して活動・事業を展開する。 - ● 連携・協働の原則 多様な地域生活課題を受け
住民や地域の関係者との協働促進に関する経験知と信頼、幅広いネットワークを基盤として地域福祉推進の専門性を発揮する。
上記を実現するため、コミュニティソーシャルワークやコミュニティワーク、ケアワーク等の専門性の維持・向上に取り組むとともに、組織的な人材育成を図る。
曽於市社会福祉協議会の理念
人と人とのつながりを大切に 地域と共に歩む
曽於市社会福祉協議会の基本方針
① 常に透明性と中立・公平性を確保し、情報公開と説明責任を果たし、地域に信頼される安定した組織経営を目指します。
② 校区社協を基盤に地域の関係機関・団体との連携強化を図り、住民主体の福祉コミュニティを目指します。
③ 地域の課題解決を使命とし、柔軟性・即応性に富んだ社協らしいサービスの構築を目指します。
④ 専門的力量を発揮し、サービスの質を高め、地域福祉を推進する中核的な組織の一員として強い使命感と誇りを持って行動します。